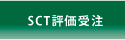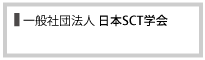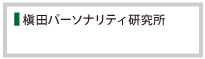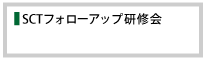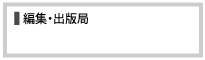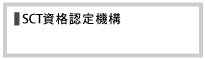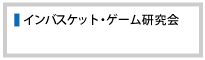JSCTA TOP > 槇田パーソナリティ研究所・研究所設立の趣旨 > コラム
![]()
会員によるコラム
《コラム3》『SCT(文章完成法テスト)活用ガイド』(伊藤隆一(編著)、金子書房、2012年)刊行について
2012.06.01 伊藤 隆一(当学会会長)
このたび、『SCT活用ガイド』を刊行しました。本書は精研式文章完成法テスト(SCT)に関する活用本です。SCTがどんなところでどのように利用されているかをまとめたガイドブックであり、かつ、SCTのケースブックを兼ねています。
これまでSCTは、「産業・組織場面」での活用と「臨床・教育場面」での活用が、また、「成人用」「中学生用」「小学生用」が、それぞれ、半独立的に取り扱われてきたきらいがありましたが、本書では、それらを可能なかぎり統合的に取り扱い、解説するよう心がけました。
本書は、SCTの活用例を、私どもが組織・運営している「槇田パーソナリティ研究所」と「SCTフローアップ研修会」に所属している、おもに若手の、しかし、経験あるSCT実践家に書いてもらうハンドブック形式にしました。第1章では、SCTについて、手元にちょっと置いておいて概観したい内容、細かなお役立ち情報などについてまとめました。便利なサブ・テキストと考えていただければと思います。また、SCTに関する専門用語については、第1章で網羅的に説明してあります。第2章以下は、 (1) 企業・組織、心理臨床、福祉、教育等の実際の現場で具体的にどのような仕事がなされているのか? (2) その中で、SCTがどのように活用されているのか? (3) 各現場の生き生きとしたケースをできるだけ網羅的に集めてみたらどうなるのか? (4) 評価方法を定式化してみよう。同時に、許容できる範囲の評価方法を例示してみたらどのようになるのか? という視点で、まとめてみました。
大変残念なことに、SCTの開発者の一人で私どもの師匠である槇田仁先生が2010年に亡くなりました。先生には、第1章のもととなる紀要論文に目を通していただき、多くのご意見を頂戴し、ラスト・オーサーとしてお名前を載せることをお許しいただきました。また、最後にお会いした時には、本書の概要をお話しすることができました。改めて、ご冥福をお祈り致します。
本書は、構想から完成まで10年ちかくの年月を要しました。「あれが足りない、これを足そう」と言っているうちに、あっという間に年月がたってしまった印象です。SCTは、質問紙とは異なり、流れ作業のようには評価ができません。また、SCTは個人情報のかたまりですから、個人情報を適切に取り扱い、倫理規定を遵守することが重要です。
単にSCTを書いてもらうことをおもしろがるような、あるいは、施行者・評価者のみが利益や楽しみを得るような施行方法は厳に慎まなければなりません。評価者には、評価能力のほか、書き手の人生を追体験し、背負い込むエネルギーと胆力が必要です。実際、一度に多数のSCT評価をこなすのはかなり重い作業です。しかしそれでも、われわれは、SCTはパーソナリティの把握に非常に役に立つ技法であると確信しています。
私たちは、今後もSCTに関連した仕事を続けていく所存です。
槇田パーソナリティ研究所は、2012年はじめより、もう一人のSCT開発者である佐野勝男先生のグループの方々が運営しておられる「東京国際・キャリアダイナミックス(TCD)」、SCT関連出版物すべての刊行元である「金子書房」と3組織で研究会を立ち上げました。今後、SCTの啓蒙活動、SCTの評価技能を保証するシステム作りなどを協同で行っていきたいと考えています。
金子書房によると、これまでのSCT用紙の販売数は、成人用・中学生用・小学生用を合わせると膨大な部数になるとのことです。しかし、そのなかで私どもが使用を把握している数は僅かなもとかと思われます。どのような方が用紙を購入され、どのような方法で評価・査定をしておられるのでしょうか。大変興味ある問題です。
本書が今後長い間、SCTの標準テキストとして巷間に広まることを切に願っています。
SCTに興味のある方々が集う場がますます広がることを切に願っています。 みなさま、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
(『SCT活用ガイド』まえがき、あとがき より)
・《コラム2》セミナーJについて
・《コラム1》セミナーKについて